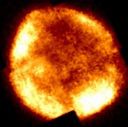昨日は風が吹きまくり。
そして今日は、雨。
ゆっくり体を休めなさいということだろう。
トンガの大地震以降体感も少々落ち着いた感じがしないでもない。
こんな日は部屋の整理するなり、本を読むなり
のんびりするしかない。
「太平洋側、夜にかけ大雨 土砂災害や増水に警戒を
日本海の低気圧の影響で、西日本や東日本の太平洋側を中心に
7日夜にかけ大雨となる見込みとして、
気象庁は土砂災害や河川の増水に警戒を呼び掛けた。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060507-00000016-kyodo-soci
どうやら大荒れの天気の模様。注意されたし。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
伊豆東方沖地震、関東平野で長い揺れ…東大地震研解析http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060507-00000402-yom-soci 「先月21日の伊豆半島東方沖の地震(マグニチュード5・4、震源の深さ7キロ)で、周期の長いゆっくりとした揺れが、関東平野全域に広がっていたことが東京大学地震研究所による地震波の解析でわかった。
周期の長い地震波が関東平野の軟らかい堆積(たいせき)層を通過する際、増幅された。また、震源が浅い地震に特有の地表付近を行き来する地震波が発生したとみられ、関東平野が地震で長く揺れやすいことを改めて示した。
地震研では、今回の地震で、固定したある位置で地盤がどれだけ揺れたかを示す値(最大変位)をまとめた。揺れの強さを表す震度に対し、最大変位は、特に長い揺れがどの範囲に広がったのかを調べるデータとなる。(読売新聞) - 5月7日11時24分更新」
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
渡り鳥ピンチ、温暖化でエサ発生時期ずれるhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060506-00000014-yom-soci「 アフリカから欧州にかけて生息する渡り鳥が減少していることが、オランダ生態学研究所の調査でわかった。
地球温暖化の影響で、エサが豊富な時期と渡りの時期にずれが生じていることが原因とみられる。英科学誌ネイチャーの最新号で発表した。
同研究所は、アフリカで越冬し欧州で繁殖する小型の渡り鳥マダラヒタキの9か所の繁殖地を調査した。
ヒナのエサとなるイモムシは、草木の芽生えに合わせて大量に発生する。調査の結果、温暖化でイモムシの発生時期は16日早まる一方、マダラヒタキの繁殖開始は10日早まっただけだった。イモムシの発生時期が特に早く、渡りとのずれが大きい場所では、マダラヒタキが過去20年間に90%も減少していた。
(読売新聞) - 5月7日1時36分更新 」
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
「明月記」記述の超新星爆発、1日で千年 衛星画像公開http://www.asahi.com/science/news/OSK200604300039.html「2006年05月01日
X線天文衛星すざくによって撮影された超新星SN1006の現在の姿(小山教授提供)
鎌倉初期の歌人藤原定家の日記「明月記」に記述が残され、人類史上最も明るく輝いたとされる超新星が発見されて1日でちょうど1000年になるのを前に、京都大理学研究科の小山勝二教授(X線天文学)らのグループが、日本のX線天文衛星「すざく」がとらえた超新星の最新画像を公開した。
この超新星はSN1006と呼ばれ、「明月記」に「寛弘三年四月二日癸酉(みずのととり)(1006年5月1日)の夜以降に騎官(おおかみ座)に大客星(超新星)が現れた」との記録が残されている。
超新星とは、太陽のような恒星が一生の最期に起こす大爆発のこと。現在は暗く肉眼では見えないが、「太陽と月を除けば、爆発時は人類史上最も明るく輝いた天体だった」と小山教授。この千年間膨張し続け、直径6光年、温度約200万度の巨大なガス球となっているという。
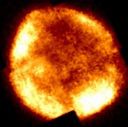
X線天文衛星すざくによって撮影された超新星SN1006の現在の姿(小山教授提供) 」
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
中国電力・島根原発近くに新活断層 広島工大など調査http://www.asahi.com/science/news/OSK200605060013.html「2006年05月06日
広島工業大、広島大などの合同調査グループは5日、松江市鹿島町の中国電力島根原発から約10キロ南東で新しい活断層を発見したと発表した。中国電力は、1、2号機の運転開始時には「周辺に安全に影響する活断層はない」とし、その後、活断層は約10キロと修正したが、今回見つかった活断層はこのさらに東の延長部にある。代表の中田高・広島工業大教授(地形学)は、「活断層の総延長は約18キロ」と主張しており、中国電力の調査の信頼性が問われそうだ。
活断層は、山すそにある休耕田を約8メートル掘ったところで見つかり、粘土や基盤岩の層が斜めに約55センチずれているのが確認できた。12万5000年前から数万年前の間に地震を起こしたと推定されるという。近く詳細な年代測定をする。
78年に策定された現行の原発の耐震指針では、5万年前までの活断層を対象とするが、今年4月にまとまった新指針案では12万〜13万年前までの活断層が対象となるため、新たに発見された活断層は確実に考慮の対象となる。
同原発周辺の活断層は、原発の南約2キロにその存在が指摘されていたが、中国電力は「考慮すべき活断層ではない」と判断し、現行の耐震基準にもとづき、2号機(89年に運転開始)は直下型地震の398ガル(マグニチュード6.5相当)を想定して建設した。1号機(74年に運転開始)の想定はこれをさらに下回る300ガル。
しかし、中国電力は3号機増設に伴う98年の調査で長さ8キロの活断層の存在を認め、04年、「万全を期す」として活断層の長さを10キロとした。
今回見つかった場所は、中国電力が認める活断層の東端から約1キロ東にあり、中田教授らは一続きの活断層とみている。
島根原発をめぐっては、地元住民らが99年、中国電力を相手取り1、2号機の運転差し止めを求め、松江地裁に提訴。地震の揺れの算出根拠となる活断層の長さが争点になっている。芦原康江・原告団長は「中国電力のずさんな調査が明らかになった。中電は検証をやり直すべきだ」と話している。
一方、中国電力は、今回の調査について「1〜3号機とも、最新の知見が出るたびに必要な耐震性は再計算し、たとえ断層の長さが20キロあったとしても、安全上の問題がないとの結論が出ている」と説明している。 」

PR