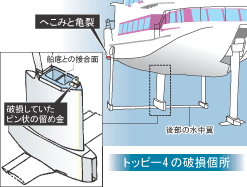とりあえず気になる記事があったので、またいつものパタンで。
トッピー衝突事故に関連して、またいろいろなことがわかってきた。
海の動物にとって人間の作った水中音波探知機(ソナー)は
とんでもない聴覚破壊兵器なんだそうだ。
「潜水艦探知用の低周波ソナーは双発ジェット戦闘機並み、中周波ソナーはロケット並みのごう音を発生させるとされ、聴覚を頼りに回遊する海洋動物を直撃した場合、致命傷となる恐れがある。」
音波を頼りにしている水中動物にとってはこれは災難だ。
トッピーの事故では大変な負傷者を出しており、
潜水艦などの硬い物体にぶつかったのではとも考えたくもなる。
そんなわけで、海底などの調査もされているようだが、結果はいかに。
スズメの大量死、クジラやイルカの乗り上げなど、どうも変だ。
便乗して毒餌を撒く人間もいるようで、人間もかなりおかしくなってきている。
(というかもともとおかしかった。)
大自然の変化の前に適応できない人間も、狂ったり大量死する可能性がある。
動物ごとではないと思うのだ。

ひろいもの
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
クジラ迷走にソナー説、高速船事故原因か…米報告書http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060415-00000004-yom-soci「米海軍の艦船の水中音波探知機(ソナー)が原因と見られるクジラの大量死や大量迷走が、過去10年間で少なくとも6回の軍事演習で起きていたことが、米議会調査局の報告書でわかった。
ソナーがクジラに害を及ぼすことは以前から懸念されていた事態で、日本近海で最近相次ぐ高速船の衝突事故との因果関係を指摘する専門家もいる。
報告書によると、最も被害頭数の大きかった例は、2年前に日米などが行ったリムパック(環太平洋合同演習)の時に米ハワイ州で観測された。演習開始直後の04年7月3日、カウアイ島ハナレイ湾で150〜200頭のゴンドウクジラが方向を見失ったように迷走していた。
ほかの5回は、演習とほぼ同じ時期に、演習海域でアカボウクジラやネズミイルカ、シャチなど小型の鯨類が数〜十数頭まとまって座礁、死んだケース。聴覚器官が損傷していた死体もあった。
潜水艦探知用の低周波ソナーは双発ジェット戦闘機並み、中周波ソナーはロケット並みのごう音を発生させるとされ、聴覚を頼りに回遊する海洋動物を直撃した場合、致命傷となる恐れがある。
米海軍は3年前、環境保護団体との間で、「日本周辺」を除く海域では、潜水艦探知用のソナーの使用を制限するとの合意書を交わした。ただ、日本周辺海域では、活発化する中国軍潜水艦の動きに合わせ、監視を強化していると言われる。
国立科学博物館の山田格(ただす)動物第一研究室長は「高速船との衝突事故も、ソナーによって、クジラの耳が聞こえなくなったことが原因というのはあり得ることだ」と話す。
一方、竹村暘(あきら)・長崎大教授は「クジラが聴覚にダメージを受けたとしても、皮膚への圧力など感覚を総動員して、船が近づいてくることを察知するはず」と、ソナー原因説には否定的だ。
◆個体増加説も◆
ほかの説もある。日本鯨類研究所の大隅清治顧問は「クジラが衝突したのだとすれば、商業捕鯨の禁止でクジラが増加したことや、高速船の便が増えたことが理由としては大きいのではないか」と話している。
(読売新聞) - 4月15日19時7分更新」
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
衝突物体の解明求める声 国交省委員会が初会合http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000205-kyodo-soci「 クジラなどとの衝突事故が相次いでいる高速船の安全運航対策を検討するため、国土交通省が設置した「超高速船に関する安全対策検討委員会」が14日、初会合を開き、出席者からは衝突した物体の早急な解明、クジラ探知装置や座席などの改良をするべきだ、との意見が相次いだ。
会合には国交省幹部や学識経験者のほか、高速船の運航事業者や造船会社の担当者らが出席。
今月9日の鹿児島県沖での衝突事故では、シートベルトをしていても骨折した乗客がいたが、会合で事業者側は「シートベルトを着用した乗客が負傷した例は過去にない」と指摘。(共同通信) - 4月14日20時38分更新」
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■
トッピー衝突 後部翼留め金も破損http://373news.com/2000picup/2006/04/picup_20060414_1.htm「鹿海保調査 想定超す衝撃か
南大隅町佐多岬沖で9日夕、鹿児島商船(鹿児島市)の高速船トッピー4が海面の物体に衝突した事故で、異物が衝突したとみられる後部の水中翼と船体をつなぐピン状の留め金が破損していたことが13日、鹿児島海上保安部の実況見分で分かった。船底2カ所に新たな亀裂も確認した。海保は留め金が破損した原因や船体に与えた影響を調べる。
留め金は後部翼の根元の突起物と船体をかんぬき状に接合している。海保は同船収容先の鹿児島ドック(鹿児島市七ツ島1丁目)で行った実況見分で破損を確認した。
同商船や同型高速船を運航する佐渡汽船(新潟県)によると、留め金は金属製で直径約8センチ、長さ14センチの円柱。後部翼に想定以上の力が加わると壊れ、翼は振り子状に後方に振られる仕組み。衝撃が船体を直撃しないよう和らげる役目を果たす。
同汽船が製造元の米ボーイング社から受けた説明では、留め金は時速80キロで重量4トン以上の物体と衝突しない限り壊れないという。トッピー4は事故当時、時速約80キロで航行していた。
鹿児島商船は「定期的に検査しており、金属疲労による破損は考えにくい」としている。
実況見分では、既に右舷後部船底のへこみ周辺で見つかった亀裂とは別に、2カ所の亀裂があったことも判明。長さは1−3センチ程度だった。船体表面から、生物の血痕や金属片などの目立った付着物は発見されなかったという。
第十管区海上保安本部の測量船「いそしお」による海底調査は同日午後も続行し、現場周辺の海底に事故に関連した落下物がないか捜索した。
海保の船体調査は13日で終了。採取試料の分析と運航会社側の聞き取り調査を続ける。 」
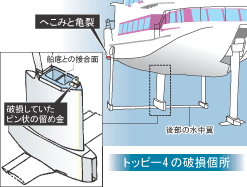
PR